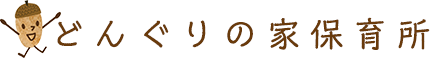大切にしていること
保育方針





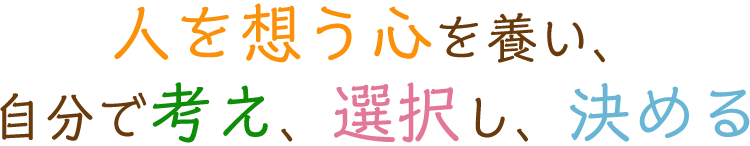

-
自己判断
-
自己決定
-
自己責任
あたたかく家庭的な、みんなで過ごせるお家の中で、豊かな思考や感性を養う。
また、一人ひとりの子どもたちが将来に必要とする責任感、判断力、決断力をもって自立に向けて成長できる環境創りをする。
保育理念
| 自分で道を切り開き、力強く、自信を持って生きていく | 一人の人間として、様々な事を選択していく。あらゆる事を自分で考えながら生活を送る。 |
| 様々な人と出会う | 担任制、クラス制ではなく、様々な人(保育者・友達)と一緒に生活を送ることで心と考え方が豊かに育つ。 |
| 異年齢保育 | 0歳~6歳の子どもたちと生活することで、自分よりも小さい子へのいたわる心が育ったり、自分よりも大きい子へ憧れる気持ちや、“真似したい“という意欲を引き出す。 |
| 生きていく上での基盤作り | 0歳~6歳の間の6年間は、生きていく上での基盤ができると考えている。この6年間で、様々な欲求を満たし、様々な経験をして、豊かな感性を養う。 |
| 一人の人間として | いくら小さくとも、一人の人間として生きていく。 保護者も子どもたちを“子ども“としてではなく、一人の人間として認め、尊重しながら、子どもたちと共に生活を送る。 |
| 生活をデザインする | 生きていく上で心地良い空間・環境をデザインしながら、それぞれが様々なことを感じながら生活を送る。 |
| バイキング方式(食事) | ”自分で選ぶ”ということを尊重し、バイキング方式にする。 あらゆる食材の栄養を知り、楽しく食事を摂る。 |
| 感謝する | 家族、自然、食べ物、自分の周りの環境に感謝することができる。 |
| 助け合って生きていく | 生活する中で、様々な人がいることを学び合い、認め合うことで、育ち合う。 |
| 生活の中に様々な学びがある | 「健康」、「人間関係」、「環境」、「言語」、「表現」を生活する中で自然に学ぶ。 |
| 保育者の個性を豊かに活かせることを重んじる | 保育者の個性が豊かなほど、子どもたちにとって、良い環境になり、その育ちが多様に広がっていくことを考える。 |
| 自然に感謝する | 空気・水・大地に生かされている事に感謝をする。また大地で育った新鮮な野菜を頂き自然に感謝する。 |
お昼ごはん

どんぐりの子ども達は毎日バイキングのお昼ごはんです。
もちろんご飯を食べられるようになった1歳の子どもたちもバイキングです。座る場所も含め全て自分で選んで自分で装います。
食べるということは活力の源(生きる)であり心を豊かにしてくれることです。
もともとは月に一度のスペシャルランチでバイキングを行っていました。
“食べられないものは無理に食べなくてもよい”という考えのもと様々なスタッフが子ども達の食事を見守ってきました。そんな中“食べなければいけない”と一生懸命食べる子がいました。
子どもも大人と同じ人間です。
体調や情緒面においてもその日によって一人一人様々なケースがあるにも関わらず全員が出された食事を最後まで食べきらなくてはならないことに疑問を持ちました。そこで子ども達がバイキングを喜びたくさんおかわりをしていることに気が付きスタッフ全員で話し合い今のバイキングになりました。

このランチの時間に子ども達の心の変化や体調に気が付くことが只々あります。
体調では主に水分や果物を沢山とった後体調を崩すことがあります。自分の身体を自分が良く知っているからこそ水分を沢山取っていたのだと思います。
また子ども達の心の変化に気が付くことがあります。昨日まではバランスよく全部のおかずをよそり嬉しそうに食べていた子どもが急に偏って装ったり座る場所を隅っこに選んだりします。
身体のバロメーター心のバロメーターを私達大人はそこで気づくことができます。

「お腹が空いた」「食べたい」というこの身体の欲求が食べると発信されます。
しかし食べなさい食べなければいけないと他者から要求されると、身体は食べることを要求していてもその要求が何等かの違う形で食べたくないと発信されてしまうのです。
そこで私たちは食べるという事は全てに元気を貰える事だと子ども達に伝え楽しい豊かなランチTimeの環境創りをしています。